預り金とは、役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を、会社や店舗が一時的に預かったときに使う勘定科目です。預り金は、本人に返金される場合もあれば、第三者への支払いに充てられる場合もあります。今回は、預り金の仕訳について解説します。
預り金の仕訳
ここからは、預り金の仕訳について簡単に解説します。
預り金の仕訳①お金を一時的に預かったとき
例)従業員の給料200,000円から源泉所得税10,000円を預かり(差し引いた)、残りを現金で支給した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給料 | 200,000円 | 預り金 | 10,000円 |
| 現金 | 190,000円 | ||
従業員の給与から所得税を天引きしたときは、それを納付するまで預かったと考えて「預り金」に仕訳をします。預り金は負債のため、預り金が増加するときは貸方に記入します。
預り金の仕訳②預かったお金を税務署に納めたとき
例)従業員から預かった源泉所得税10,000円を税務署に現金で納めた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
給料から差し引いて預かった源泉所得税を税務署に納めると、「預かったお金を納付する義務」が果たされます。仕訳では、「預り金」という負債が減少すると考えるため、借方に記入します。
預り金に含まれるもの
預り金でイメージしやすいのは、従業員の給料から天引きする「源泉所得税」や「住民税」や「社会保険料」でしょう。この場合の預り金は本人には返済されず、第三者へ納付されます。
預り金は流動負債
また預り金は、あとで返済や支払いをする義務があるため、貸借対照表の負債、その中でも流動負債に含まれます。そのため、預り金に含まれるのは、決算日の翌日から1年以内に返済期日が来るものです。1年を超えると、固定負債の「長期預り金」になります。
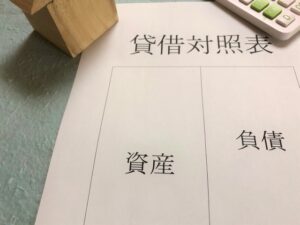
預り金と間違えやすい勘定科目
簿記の初心者の方は特に、似たような勘定科目について間違えて理解してしまう場合があります。そこで、預り金と混同されやすい勘定科目についても、その違いについて理解できるように解説します。
未払金
未払金とは、商品以外のものを購入して後払いにした代金のことを指します。商品の仕入であれば「買掛金」という勘定科目になりますが、未払金は商品以外の購入で使う科目です。預り金と同じく流動負債に分類されます。
前受金
前受金とは、いわゆる「手付金」や「内金」を受け取ったときに使う勘定科目です。流動負債に入ります。負債に入るのは違和感があるかもしれませんが、商品を引き渡せなかった場合に、前受金は返還義務が生じるため負債に分類されます。

前払費用
前払費用とは、一定の契約に従って継続して役務の提供を受ける場合に、まだ提供を受けていない役務に対して当期に支払った対価のことです。言葉にするとやや難解ですが、たとえばオフィスを賃貸で借りたときに、家賃は前払いになることがほとんどです。その前払家賃は、前払費用に含まれます。その他、前払保険料などが前払費用に該当し、流動資産に分類されます。

預り金のまとめ
今回は、一時的にお金を預かるときの仕訳について解説しました。預り金は、「従業員の所得税や社会保険料などを会社や店舗が本人に代わって納付するために一旦預かるお金」と、お金の流れをシンプルに考えると理解しやすいかもしれません。預り金とは反対に、お金を立て替えるときの勘定科目は「立替金」です。








